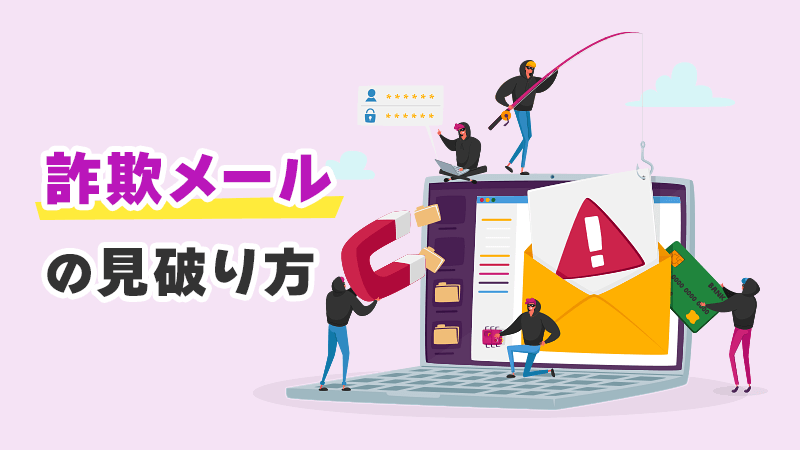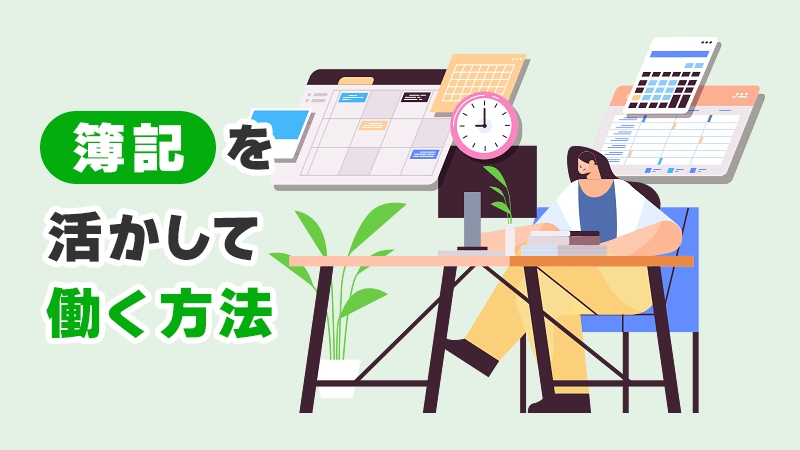突然届く、不審なメール。
「アカウントが停止されました」「本人確認が必要です」など、あわてて開いてしまいそうになるような文面で、差出人には見慣れた企業名が表示されている――。
それ、実は巧妙な“なりすましメール”かもしれません。
日本国内でも詐欺メールによる被害は増加傾向にあり、警察庁の統計によると、2023年の特殊詐欺による被害総額は約452.6億円に達しました。
しかも被害にあった人の多くが、「自分は大丈夫」と思っていた一般の利用者です。
この記事では、実際に日本で発生した詐欺メールの手口や見破るポイント、被害を防ぐための実践的な知識を紹介します。
メールやSMSを日常的に使っている方こそ、一度しっかり確認しておきましょう。
詐欺・なりすましメールとは
詐欺・なりすましメールとは、正規の企業や公的機関を装って、個人情報や金銭をだまし取ろうとするメールのことです。
見た目は本物とそっくりですが、実際には詐欺グループが作った偽物です。
たとえば「支払いに問題があります」「アカウントが停止されました」といった内容で、添付ファイルやリンク先に誘導するのが典型的なパターンです。
最近では、メールだけでなくSMSやSNS経由でも同様の詐欺が広がっており、注意が必要です
実際に日本で起きた詐欺メールの手口
日本国内では、実在の企業名をかたった詐欺メールの被害が多数報告されています。
有名企業を装ったケース
2023年には、Amazonをかたるフィッシング詐欺が全国的に急増しました。
「ご注文の確認」や「セキュリティチェックが必要です」といった件名のメールが届き、リンクをクリックすると偽のログインページへ誘導されます。
そこにIDやパスワードを入力すると、アカウントが乗っ取られたり、登録済みのクレジットカード情報が盗まれてしまうのです。
金融機関を偽装する手口
三井住友銀行やPayPay銀行を装ったメールでは、「不正アクセスが確認されました」といった内容で、ログイン情報の入力を求められた例が多数報告されています。
いずれも、正規サイトに酷似したデザインが使われており、一見して見抜くのは困難です。
証券会社の不正アクセス事例
近年は、詐欺メールの手口が進化し、証券会社のオンライン口座を狙った被害も急増しています。
2025年1月から5月までに、楽天証券やSBI証券などの大手証券会社の口座で、累計1万件以上の不正アクセスが発生し、不正な売買による被害総額は約2,700億円に達したと金融庁が報告しています。
この手口では、詐欺メールに記載された偽のログインページにIDやパスワードを入力させ、さらに二段階認証コードまで奪うケースが増加。
結果として、本人の知らないうちに株の売却や買付が行われ、多額の資産が流出しています。
証券口座を安全に守るためにも、メールの真偽を見極め、多要素認証の設定を必ず行うことが重要です。
被害額と件数
警察庁の公式データによれば、2023年のフィッシング詐欺によるインターネットバンキング不正送金被害は、発生件数が約5,578件、被害額は約87.3億円にのぼりました。
また、オレオレ詐欺などを含む特殊詐欺全体では、認知件数約19,038件、被害総額約452.6億円に達しています。
参考:警察庁「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」
参考:警察庁「フィッシングに関する注意喚起ページ」
詐欺メールの見分け方
では、こうした詐欺メールをどう見抜けばいいのでしょうか?
実際のメールを見ると、いくつかの共通する特徴があります。
差出人のメールアドレスに注意
表示名が「Amazonカスタマーセンター」などとなっていても、メールアドレスのドメイン部分(@以降)をよく見ると、不審な文字列が含まれていることがあります。
たとえば、「@amazon-support.com」「@amazon.jp.com」など、一見それらしくても正規の企業とは無関係なドメインです。
リンク先URLを確認する
リンクをクリックする前に、URLにマウスカーソルを合わせて確認しましょう(スマホなら長押し)。
正規の企業なら「https://www.amazon.co.jp/」などのようなアドレスですが、詐欺サイトでは似た文字列や「.com」「.xyz」など、違和感のあるドメインが使われています。
また、暗号化されていない「http://」のリンクは特に要注意です。
不自然な日本語や急かす表現
「至急ご対応ください」「本日中に確認が必要です」など、不安をあおる表現も詐欺メールの典型です。
加えて、文法が不自然だったり、日本語の言い回しに違和感がある場合は疑ってかかりましょう。
被害に遭わないためにできること
詐欺メールを100%シャットアウトするのは難しくても、被害を防ぐ方法はいくつかあります。
メールソフトやセキュリティ設定の活用
多くのメールサービスでは、「迷惑メールフィルター」や「なりすまし検出機能」が用意されています。
GmailやYahoo!メールなどでは自動で判別されることもありますが、設定が有効かどうか確認しておくことが重要です。
また、ウイルス対策ソフトの導入と定期的な更新も忘れずに行いましょう。
おかしいと思ったらすぐ確認・通報を
少しでも怪しいと感じたら、まずその企業の公式サイトにアクセスし、メールの真偽を確認しましょう。
不審なメールは「フィッシング対策協議会」に通報することで、被害拡大を防ぐ手助けにもなります。
また、身近な人に相談することも大切です。
家族や職場でも情報共有を
詐欺メールは、ITに詳しくない人ほど騙されやすい傾向があります。
特に高齢の家族や、職場の同僚などと、「こういうメールが増えているらしいよ」と声をかけ合うだけでも、被害の予防につながります。
まとめ
詐欺メールは、年々巧妙さを増しています。
しかし、その多くはちょっとした違和感に気づけば、未然に防げるものばかりです。
差出人やURLの確認、不自然な文面への注意、そして不審に感じたらすぐに調べる。
この3つを意識するだけで、被害の可能性はぐっと減らせます。
自分自身を守るため、そして周囲の人も守るために、今日から少しだけ“メールを見る目”を養ってみてください。