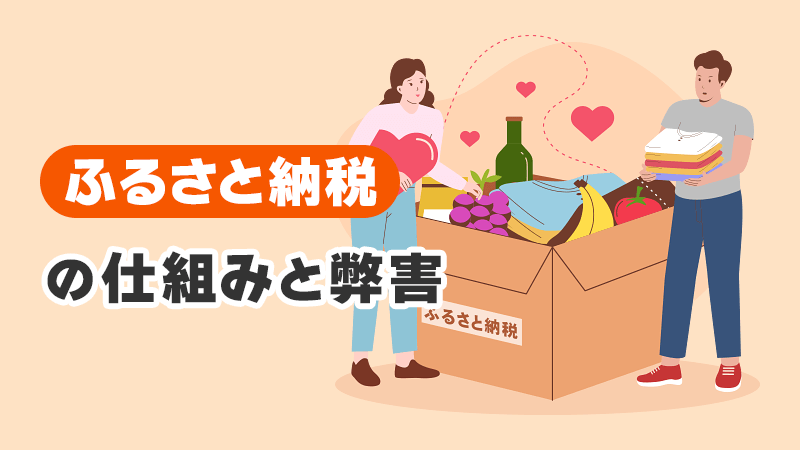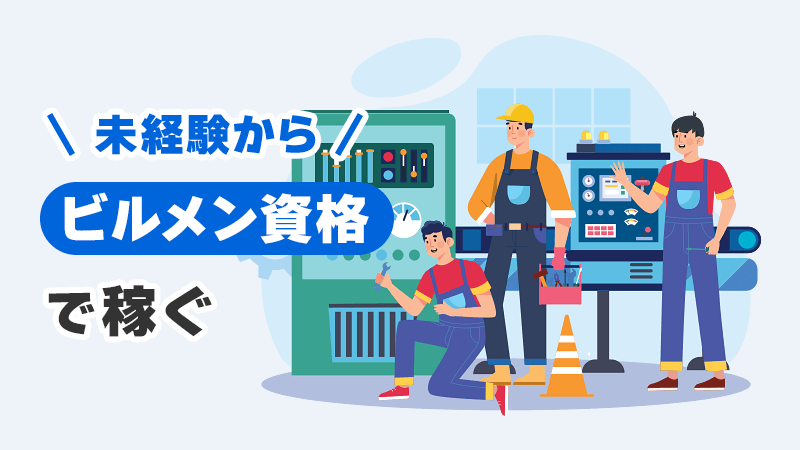ふるさと納税って、最近はすっかり身近な制度になりましたよね。
「おいしいお肉がもらえる」「年末の恒例行事になってる」なんて声もよく聞きます。
でも実は、この制度、表向きには見えない“ちょっとした裏事情”もあるんです。
この記事では、ふるさと納税の仕組みをざっくりおさらいしつつ、なかなか知られていない制度の“影”の部分も丁寧に解説します。
これを読めば、「お得」なだけじゃないふるさと納税の姿が、少し違って見えるかもしれません。
ふるさと納税ってどんな制度?
まずはサクッと仕組みから。
ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄付をして、その分の税金を控除してもらえる制度です。
控除されるのは、所得税と住民税の一部。
寄付額のうち2,000円を引いた分が、翌年の税金から差し引かれます。
つまり、自己負担2,000円で、地域の特産品をお礼にもらえるわけですね。
制度をうまく使えば、普段は手が出ないような高級グルメを“実質タダ”で楽しめるというわけです。
やり方も簡単で、ふるさと納税サイトで寄付先を選んで手続きするだけ。
確定申告が面倒なら「ワンストップ特例制度」を使えば、書類1枚でOK。
この気軽さが、若い世代にも広がっている理由のひとつです。
実は、いいことばかりじゃない?
制度として便利でお得なふるさと納税。
でも、その裏ではちょっと気になる“副作用”もあるんです。
都会の税金がごっそり地方へ
ふるさと納税を使うと、本来自分が住んでいる市区町村に入るはずの税金が、寄付先の自治体へと移ります。
つまり、たとえば東京に住んでいる人が鹿児島に寄付したら、東京の税収が減っちゃうんです。
実際、都市部ではかなりの減収が出ています。
2024年度(令和6年度)の見通しでは、こんなランキングになっています。
- 横浜市: 約304億7,000万円
- 名古屋市: 約176億5,400万円
- 大阪市: 約166億5,500万円
- 川崎市: 約135億7,800万円
- 東京・世田谷区: 約110億2,800万円
※数値はNHKニュース(2024年12月12日)より引用しています。
NHKニュース:ふるさと納税で都市部の税収減少が拡大
こうして見ると、「あの街、そんなに減ってるの!?」と驚きますよね。
東京都全体では、なんと約1,900億円も税収が減少していると発表されています(出典:東京都主税局)。
その影響で、都会の保育・医療・道路整備といった“身近なサービス”に影響が出ることも。
ちょっと意外ですが、「地元のサービスが減る原因を自分で作ってた」なんてこともあるんです。
返礼品競争が過熱しすぎた時代
ふるさと納税といえば、やっぱり気になるのは返礼品ですよね。
地域の特産品だけでなく、過去には高級家電や商品券まで登場して、「これ本当に寄付?」とツッコミたくなるような状況もありました。
そんな状態を見かねて、総務省が「返礼品は寄付額の3割以内、地場産品に限る」とルールを強化。
2023年にはさらに厳しくなり、送料や加工費まで含めて3割以内にするよう求められています。
とはいえ、まだ「お得感」だけで寄付先を選んでいる人も多く、制度本来の「地域を応援する」っていう目的が見えづらくなっているのも現実です。
返礼品、本当に“地元産”?
名前だけ地元だけど、実は製造は別の地域だったり、委託業者が地元と関係なかったり…。
こういうケースも少なくありません。
「この返礼品、地元関係ないのでは?」というツッコミが入るような状況もあり、制度の意義があやふやになってしまうこともあります。
せっかくの寄付が、地元産業の活性化に繋がっていないなんて、ちょっともったいないですよね。
制度の見直し、少しずつ進んでます
こうした問題に対応するために、制度の見直しが進んでいます。
総務省は返礼品のルールをさらに細かく定めて、自治体が“返礼品目当ての寄付集め”に走りすぎないようにブレーキをかけました。
また、自治体側も、返礼品だけに頼らず「体験型」の返礼品や地域のストーリーを伝えるような工夫をし始めています。
たとえば、その土地の文化体験やオンラインツアーなど、物ではなく体験を通じて地域に興味を持ってもらう。
こうした取り組みが、少しずつ広がってきています。
ふるさと納税、どう使えばいい?
お得で便利な制度なのは間違いない。
でも、「得すること」だけが目的になってしまうと、本来の良さを見失ってしまうかもしれません。
せっかく寄付するなら、「どんな地域を応援したいか」「どんな自治体の取り組みを応援したいか」といった視点で選ぶと、より満足度の高い納税になります。
あともうひとつ忘れたくないのが、自分が住んでいる地域のこと。
ふるさと納税を使いすぎて、地元の税収が減ってしまうこともあるので、自分の暮らしの場所にも少しだけ意識を向けてみるのが大切です。
「ふるさと」と「今住んでいる場所」のどちらも大切にする。
そのバランスが、これからの納税のカギかもしれません。
おわりに
ふるさと納税は、うまく使えば「地域支援」と「自分のお得」が両立する制度です。
でも、その裏にはいくつかの課題もあるということを、少しだけ頭の片隅に置いておくと、制度との付き合い方も変わってきます。
寄付する場所をただ“得”で選ぶのではなく、「応援したい気持ち」で選ぶ。
そんなふるさと納税の使い方が、これからもっと増えていくといいですね。