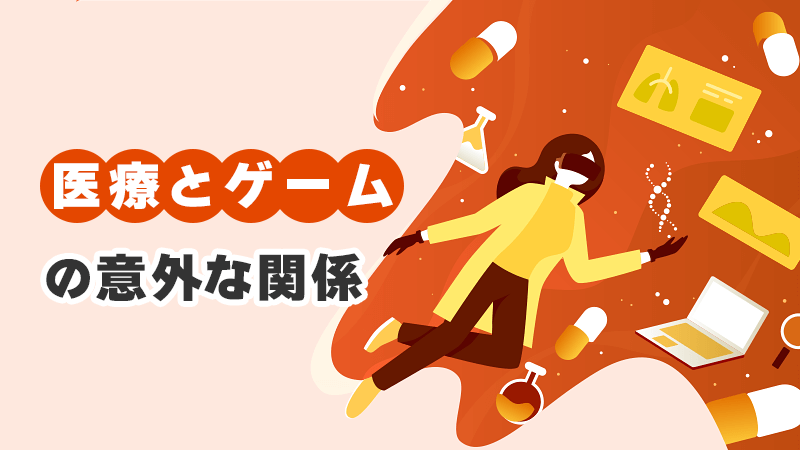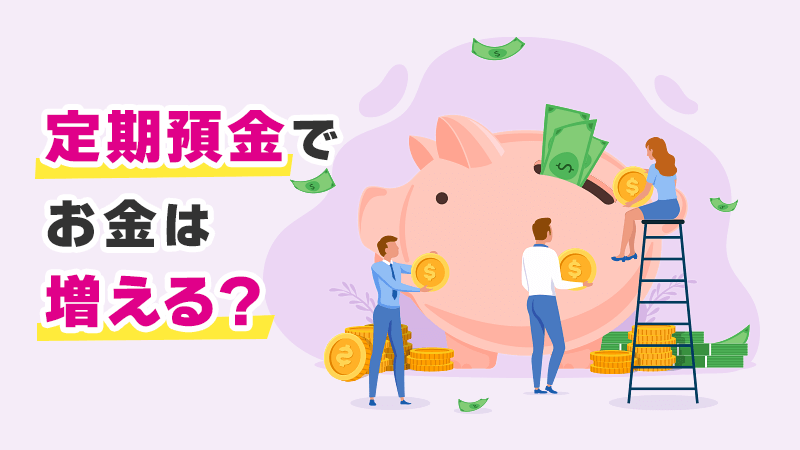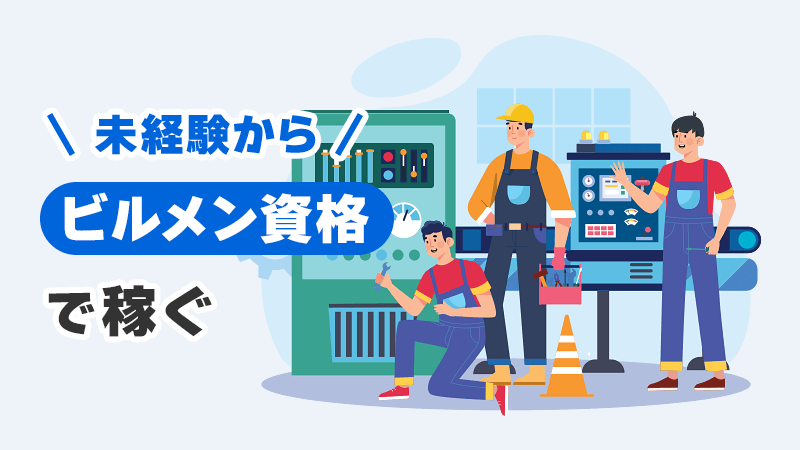こんにちは、限界ゲーマーの神掛 杉守です。
ボス戦をノーダメージでクリアした時、「この反射神経、現実でも使えないかな…」と考えたことがあります。
今回は「医療とゲームの意外な関係」の話をしていきます。
医療とゲーム?
ゲームって、敵を倒したり、スコアを競ったり、娯楽のイメージが強いですよね。
でも実は、リアルな医療の現場で、手術の練習やリハビリ支援にゲームが使われているって知ってました?
この記事では、外科手術から災害救助、高齢者支援まで、ゲームがどんなふうに医療に関わっているのかをご紹介していきます。
実はこの技術、私たちの「医療費」や「経済」に大きく関わってくるんです。

医療とゲームって意外と相性いいのか…。
俺も外科医になったらゴットハンドと呼ばれるかも!?
VRで手術を学ぶ
手術とゲーム。一見まったく無関係に思えるかもしれませんが、実は最近では「VR手術トレーニング」が医療現場で注目されています。
本格的な医療向けVRで言えば、「PrecisionOS」の名前は外せません。
これは整形外科手術を対象にしたVR学習ツールで、骨や筋肉の構造が忠実に再現されています。
しかも、手術室の雰囲気やチームワークまで体験できるという徹底ぶり。
カナダやアメリカではすでに教育機関での導入が進んでいて、学習者は「手を動かして覚える」ことができると評価されています。
手元操作の大事さは、格ゲーと同じですね。
実は、このトレーニング、コスト効率がめちゃくちゃ良いんです!
高価な医療用具や消耗品、さらには生体モデルを使うことなく、新人医師が何度でも練習できる。
教育にかかる費用や時間を大幅に削減できるのは、病院経営にとってもマジで重要なポイントですね。
さらに進んだ技術としては、「VirtaMed LaparoS」があります。
これ、リアルな器具を実際に手に持ちながら、仮想体内を操作する“複合現実(MR)”の手術シミュレーター。本物の手応えを感じながら、画面では臓器の内部を動かすという、まさに「リアルとバーチャルの融合」です。

実際の手術さながらの臨場感と本物そっくりの表現力はすごい!
VRは実際に目の前の患者がいると錯覚しそう。
さらに仮想とリアルを合体させたMRシミュレーター、どこまで技術は進むのかな。
看護・救急現場でもVRが活躍
医師だけじゃありません。
看護師や救急救命士など、医療の現場で働く人たちにとってもVRは強い味方です。
「SimX」は、そんな現場で働く人向けに開発されたVRトレーニングプラットフォーム。
たとえば、バイタルチェック、応急処置、患者との対話といった対応を、まるで本物のようにシミュレーションできます。
しかも、VRゴーグルがあればどこでもトレーニングができるので、時間や場所の制約を受けにくいのも魅力。
特に注目されているのが、「SimX VALOR」は、米空軍と共同開発された軍医療向けVRトレーニングで、災害や戦場を想定したシナリオが特徴です。
日本国内ではまだ導入事例は限られていますが、医療・防災分野での活用に向けて注目され始めています。
医療スタッフの「現場力」を育てるために、ゲームの持つ再現性や反復練習のしやすさが役立っているんですね。

いきなりぶっつけ本番だと思うように動けない…。
そんな医療の現場では本物さながらのクオリティが助けになるんだな。
一般プレイヤーが体験できる医療系ゲームも
医療向けVRは本格的すぎて、一般の人が実際に触れる機会はなかなかありません。
でも「医療の雰囲気」を少しだけでも体験できるゲームもあります。
そのひとつが、「Surgeon Simulator: Experience Reality」。
PlayStation VRやSteamで遊べるVRゲームで、ブラックジョークを交えた操作感や手術体験が特徴。
あくまで“エンタメとしての医療ゲーム”ですが、手術室の視点やツールの扱いなど、リアル寄りな部分も意外と多いんです。
本気の医療現場とは違うけれど、ちょっとだけ“命を預かる重み”を体験してみるにはぴったりかもしれません。
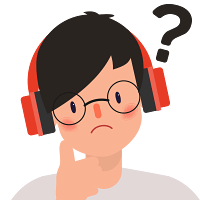
俺にできるのは、せいぜいゲーム上の手術台に立つことくらい。
ちょっとふざけてるけど、医療体験ゲームとしてはユニークな存在だね。
高齢者のリハビリにもゲームが登場
医療の話というと手術や救命のようなハードな話が中心になりがちですが、もうひとつ注目したいのがリハビリ分野。
ここでもゲームが活躍しています。
たとえば、サン電子工業株式会社が開発している「PON PON TOUCH! Ver2」や「ドキドキへび退治Ⅱ」など。
どれも高齢者福祉施設向けに作られたリハビリ用ゲームです。
操作は簡単で、体を使って遊びながら運動ができる設計になっています。
高齢者の方にとって、リハビリは「やらなきゃいけない」ことですが、気が乗らなかったり、長続きしなかったりするのが現実。
だからこそ、ゲームという“楽しい仕掛け”が重要になってくるわけです。
スコア表示や音のフィードバックなど、ゲームらしさがモチベーションを生んでいます。
しかもこれ、理学療法士の方々からも好評で、実際に成果が出ているケースもあります。
楽しみながら動けるというのは、まさにゲームの本領発揮ですね。

ゲームセンターのゲーム機に見えるけど、中身はしっかりリハビリ向け。
内容はずっと簡単になってるらしい。
どんな年齢でもゲームって楽しいものだしな!
まとめ
医療とゲーム、一見するとまったく違う世界に見えるかもしれません。
でも実際は、手術のトレーニングから救急対応、高齢者のリハビリまで、いろんな場面でゲームが活用されてるんですね。
つまり、ゲームは「命」だけでなく、「お金」の問題も解決してくれるかもしれないんです。
例えば、高額な医療機器を何度も使わずに済むから、教育コストが安くなる。
医師や看護師のスキルが上がれば、医療ミスも減って賠償リスクも減る。
リハビリが楽しく続けば、介護費用や社会全体の医療費も抑えられるってわけです。
この「医療×ゲーム」って、未来の医療サービスを効率よく回すための、最高の投資かもしれませんね。
技術が進めば進むほど、ゲームのリアルさやインタラクティブ性が医療と相性が良くなるんですよね。
今後はAIやセンサーとの連携でもっとリアルなトレーニングが可能になると言われています。

医療の現場でゲームが本気で役立っているなんて、正直驚きました。
画面の中だけが戦場じゃない。誰かの命を支える技術になってるんですね。
改めてゲームってすごいなって思いました!