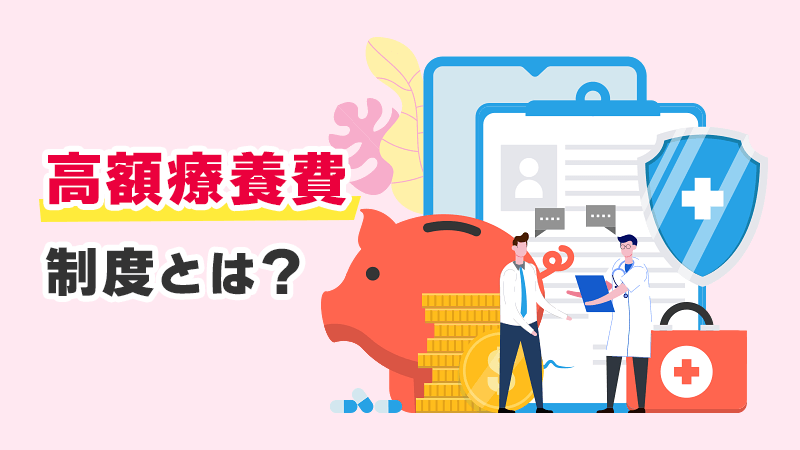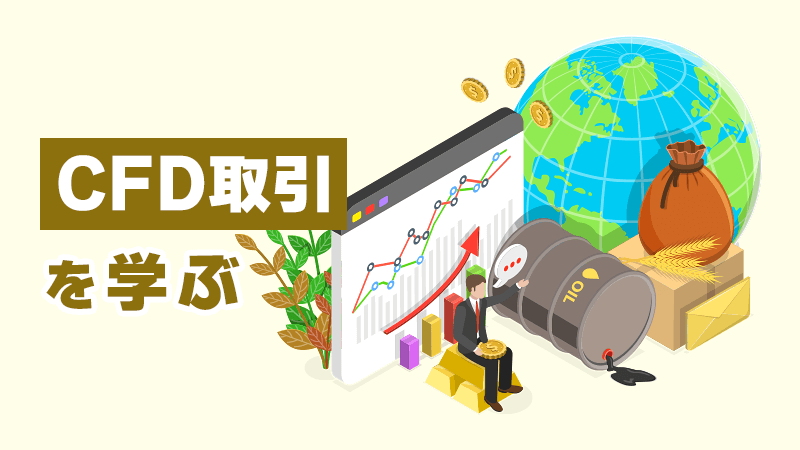思ったより医療費が高くてびっくりした、なんて経験ありませんか?
入院や手術になると、何十万円もの医療費が一度にかかることも珍しくありません。
でも、ちょっと安心してください。
日本には「高額療養費制度」という、医療費が高額になったときに助けてくれる制度があります。
この記事では、この制度がどんな仕組みで、実際にどれくらいお金が戻ってくるのか、そして今後どう変わっていく可能性があるのかを、わかりやすく丁寧にお伝えしていきます。
高額療養費制度ってなに?
簡単に言うと、「1ヶ月の医療費がすごく高くなったら、上限を超えた分はあとから戻ってくる」制度です。
日本の公的医療保険に入っていれば、基本的に誰でも対象になります。
たとえば、入院して医療費が100万円かかったとしても、3割負担なら30万円。
でも、この制度を使えば、自己負担は実はその半分以下になることもあるんです。
実際、どれくらい負担が減るの?
医療費って入院や手術となると一気に何十万円とかかることもあって、高くなりそうでちょっと怖いですよね。
でも、高額療養費制度を使えば、実際に払う金額はかなり抑えられます。
たとえば、69歳以下で会社員、年収が370万〜770万円くらいの人の場合。
このあたりの収入帯だと、1か月に払う医療費の上限は「8万円ちょっと+α」という感じになっています。
もう少し正確に言うと、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」という計算式です。
たとえば医療費が100万円かかったとしても、自己負担はだいたい9万円前後におさまるんです。
本来なら30万円近くかかるところなので、かなりの差ですよね。
さらに、年間を通して医療費が高額になることがある人には「多数該当」という制度が強い味方になります。
これは、過去1年間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合に適用され、4回目以降の自己負担上限額がぐっと引き下げられる仕組みです。
例えば、一般所得(多くの会社員や自営業者の方が該当する所得層)の方であれば、月の負担が約44,400円で済むようになるんです。
※金額は厚生労働省「高額療養費制度のご案内(2023年9月版)」に基づいて記載
使うにはどうしたらいい?
高額療養費制度は、自動で適用されるわけではありません。
ちょっとした準備が必要ですが、最近はよりスムーズに使える方法もあります。
マイナ保険証を使えば申請不要なケースも
マイナンバーカードを健康保険証として登録(マイナ保険証)していると、「限度額適用認定証」がなくても、窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。
つまり、事前に申請しなくてもOKなケースがあるんです。
ただし、これは「住民税がかかっている世帯」が対象です。
会社員や自営業の方など、毎年ある程度の収入がある人はたいていこの中に含まれます。
反対に、年金や生活保護などでほとんど収入がない場合は「住民税非課税世帯」となり、この自動適用の対象外になります。
この場合は、これまで通り「限度額適用認定証」を事前に取得しておく必要があります。
認定証を用意しておくのもアリ
マイナ保険証を使わない・使えない場合や、住民税非課税世帯の方は、従来通り「限度額適用認定証」を取得しておくと安心です。
手続きは、保険証を発行しているところに申し込めばOK。
会社員の方は、加入している医療保険の運営元(協会けんぽや健康保険組合など)に。
国民健康保険に入っている方は、お住まいの市区町村が窓口になります。
申請を忘れてしまっても、支払い後に申請すれば2年以内であれば超えた分が戻ってきます。
ちょっと手間はかかりますが、やらない手はありません。
実はカバーできない費用もある
注意したいのは、この制度で全部がカバーされるわけじゃないこと。
たとえば、入院中のご飯代や、個室の料金(いわゆる差額ベッド代)は対象外で全額自己負担になります。
快適な病室を選ぶと、それだけでプラス1〜2万円/日なんてことも。
あと、月をまたいだ入院も注意が必要です。
制度の計算は「1日〜月末」単位なので、月末に入院して翌月にまたがると、2ヶ月分として扱われて2回分の上限額がかかってしまうんです。
ちょっとしたことですが、知っておくと余計な出費を防げます。
年収が高い人ほど負担が重くなる?
実はこの制度、収入が高い人にはちょっと厳しめです。
というのも、自己負担の上限額は「たくさん稼いでる人は、たくさん払えるでしょ」という前提で決まっているんです。
年収が1,160万円を超える人だと、月の上限が30万円近くになるケースもあります。
つまり、同じ100万円の医療費でも、収入によって戻ってくる額が全然違うということ。
差額ベッド代や食費なども含めると、負担感は思った以上かもしれません。
制度改正の動きにご注意!
高額療養費制度の自己負担額、もしかしたら変わるかもしれないって知ってましたか?
実は、2025年8月からの自己負担上限額の見直しが進められていたんです。
具体的には、年収に応じて上限額が5〜15%引き上げられる案が出ていて、特に高所得者にはかなりの負担増になる予定でした。
でも2025年3月に国民の理解が得られていないことなどを理由に、いったんこの改正案は見送られました。
とはいえ、今後また再検討される見込みで新しい方針が出るかもしれません。
つまり、まだ終わっていないということです。
今のうちにできる備えって?
「改正されるかもしれない」なら、今からできることをやっておくのが得策です。
まずは、自分がどの所得区分に入るか確認してみましょう。
給与明細や源泉徴収票を見れば、おおよその年収がわかります。
そして、マイナ保険証もしくは限度額適用認定証はなるべく早めに手に入れておくのがおすすめ。
使うタイミングが急に来ることもありますし、手続きに慣れておく意味でも取っておいて損はありません。
さらに、制度でカバーできない部分を民間の医療保険などで補っておくのもひとつの選択です。
食事代や個室代が長期化すれば、それだけでも結構な金額になります。
まとめ
高額療養費制度は、知らないと損をすることがある一方で、知っていれば安心感がグッと高まる制度です。突然の入院や手術は、誰にでも起こりうるもの。
でも、そのときに制度の存在を知っているかどうかで、心の余裕がまったく違います。
この先制度がどう変わるかはまだわかりませんが、今の仕組みをしっかり把握してできる準備はしておきたいところです。
「まだ先の話だからいいや」と思わずに、今ちょっと調べておくだけで、将来きっと自分を助けてくれるはずです。